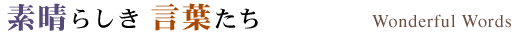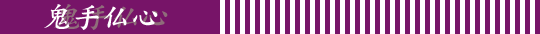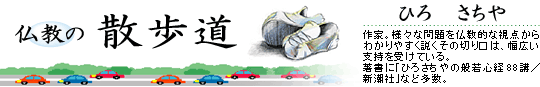第二期祖師先徳鑽仰大法会
両内局が出仕で開闢法要を厳修
天台宗では、平成24年4月から平成34年3月までの10年間に亘って「祖師先徳鑽仰大法会」を奉修しており、第一期では平成25年の慈覚大師一千百五十年御遠忌法要など、様々な事業を展開してきた。本年4月からは第二期に入り、1日には、総本山延暦寺根本中堂において、木ノ下寂俊天台宗宗務総長を始めとする天台宗内局並びに小堀光實延暦寺執行ら延暦寺役職者、延暦寺一山住職の出仕の下、開闢法要(かいびゃくほうよう)を厳修、第二期大法会の円成を祈願した。
 大法会第二期では、平成28年に宗祖伝教大師御生誕一千二百五十年、恵心僧都一千年御遠忌、平成29年には相応和尚一千百年御遠忌、平成33年には伝教大師一千二百年大遠忌を迎える。
大法会第二期では、平成28年に宗祖伝教大師御生誕一千二百五十年、恵心僧都一千年御遠忌、平成29年には相応和尚一千百年御遠忌、平成33年には伝教大師一千二百年大遠忌を迎える。この開闢法要をスタートとし、いよいよ大法会円成に向け宗内のムードも高まりつつある。
天台の教えと行、それぞれに大きな足跡を残された祖師方を偲び、その功績を讃える第二期の大法会。この開闢法要に際し、木ノ下宗務総長は「この大法会において、祖師方の解行双修(げぎょうそうしゅう)の足跡をたどることは、世界の平安と人々の安寧のために示されたみ教えと、信仰を尋ね求める千載一遇の御勝縁であります。戦後七十年を迎えた今、その意義は深いものがあり、宗徒の皆様、檀信徒の皆様とともにこの大法会が魔事なく円成することを願うところであります」と、心新たに決意を述べている。