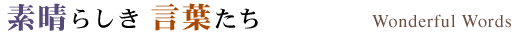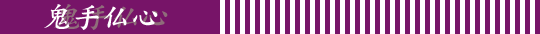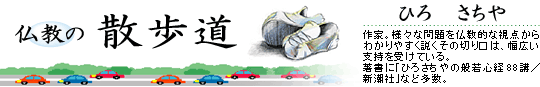インド・禅定林の大本堂完成
天台宗開宗千二百年慶讃大法会の記念事業として進められていた、インド・禅定林(サンガラトナ・法天・マナケ住職)の大本堂がほぼ完成し、本年二月八日には落慶式典が盛大に執り行われる。この大本堂は、インド仏教の精神的象徴となるばかりではなく、天台宗の教義に基づく大乗仏教布教の一大道場となる。また、世界平和の祈りの場となることを目的としている。
 サンガラトナ・法天・マナケ師は幼くして来日し、比叡山で修行した後、インド共和国に帰国。現在バンダラ県・ポーニ市ヤード村で禅定林を主催し、仏教活動を続ける一方で、パンニャ・メッタ・サンガ(P・M・S)の代表を務めている。
サンガラトナ・法天・マナケ師は幼くして来日し、比叡山で修行した後、インド共和国に帰国。現在バンダラ県・ポーニ市ヤード村で禅定林を主催し、仏教活動を続ける一方で、パンニャ・メッタ・サンガ(P・M・S)の代表を務めている。P・M・Sは、孤児院「パンニャ・メッタ子どもの家」や、ナグプールで「パンニャ・メッタ学園」、体育館、図書館等を運営している。特に図書館は識字率の向上に取り組むインドにおいては貴重な施設で、数千冊の蔵書があり、毎日百人以上が利用している。
一方、宗教面でインドは、仏教発祥の地にもかかわらず、仏教不在の時代が約八百年間続いた。
第二次大戦後、「人間平等」を主張するピームラオ・ラムジー・アンベドガル博士は、「インドが抱える諸問題を解決するためには、仏教の精神が必要」とヒンドゥ教から仏教に改宗し、活動を始めた。しかし、依然インドではカースト制度が深く根を下ろし、差別と貧富の上に社会が成り立つ構造は変わらなかった。
インドにおいて、もう一度仏教を再生しようとしたアンベドガル博士の遺志を継いだサンガ師は、伝教大師が唱えられた「国宝的人材」の育成こそが天命と痛感、仏教の教えが底辺で生きる人々の希望の光としてなくてはならない存在であると実感し禅定林大本堂の建立を発願した。
大本堂は、サンガ師を中心にパンニャ・メッタ協会日本委員会(P・M・J)の協力のもと建設が進められ、平成十七年に地鎮祭が執行された。釈尊の故郷インドに再び大乗仏教に基づく平等精神を弘める象徴としての意味を持ち、人種・民族・宗教・宗派を超えて人々を受け入れる「智恵と慈悲」の結晶となる。
また、日本および諸外国からの修行者を受け入れ、人材育成道場の役割も果たすが、サンガ師は「インド大乗仏教の灯火となり、仏教発祥の大地や空気に触れることによって、仏教のみ教えを体得してもらいたい」と語っている。
本年は、アンベドガル博士の没後五十年であり、禅定林開創二十年の記念の年でもある。